「キングダムはいつの時代?」と気になって調べている方へ、この記事では『キングダム』の時代設定を中心に、日本やヨーロッパと比較した歴史的背景を紹介。
さらに、春秋戦国時代の史実、主人公・信のモデルや戦術、地図で見る戦国七雄の勢力図、そして結末に向かう歴史の流れまでをわかりやすく解説します。
作者・原泰久先生のこだわりや、三国志との違い、時代劇としての魅力も交えながら、いつの時代を描いた作品なのかを深く掘り下げていきます!
結論!キングダムの時代
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時代区分 | 中国戦国時代(末期) |
| 西暦 | 約 紀元前245年〜紀元前221年 |
| 主な国 | 秦、趙、魏、韓、楚、燕、斉(戦国七雄) |
| 主人公 | 信(しん)=李信(りしん)将軍がモデル |
| 同時代人物 | 嬴政(後の始皇帝)、王翦、呂不韋、蒙武など |
| 舞台となる地 | 主に秦(咸陽)、戦地として中原各地 |
| 歴史的背景 | 各国が統一を争う時代、秦が台頭して最終的に中国を統一 |
| 終着点 | 紀元前221年、秦による中国統一と始皇帝の誕生が物語のゴール |
| 歴史書の参照 | 『史記』(司馬遷)、『戦国策』など |
| 日本での位置付け | 日本人にとっての「三国志」的な人気と影響力 |
キングダムはいつの時代かを時代設定から探る

- 春秋戦国時代とはどんな時代?キングダムとの繋がり
- キングダムの時代設定と西暦での位置づけ
- 中国戦国七雄と地図から見る勢力図
- 史実に基づいたキングダムの歴史描写
春秋戦国時代とはどんな時代?キングダムとの繋がり
春秋戦国時代とは、古代中国で国同士の争いが激化した長い混乱の時代です。この時代は、紀元前770年頃から始まり、紀元前221年に秦が中国を統一するまで続きました。
なぜこの時代が重要かというと、中国の歴史の中でも特に戦争や外交、思想の発展が活発だったからです。当時は「春秋時代」と「戦国時代」に分けられ、それぞれに特徴があります。
春秋時代(紀元前770年〜403年頃)
- 周王朝の権威が弱まり、地方の諸侯が台頭しました。
- 孔子などの儒学者が活躍し、多くの思想家が登場しました。
- 国の数は100を超えていたとされ、頻繁に同盟と裏切りが繰り返されました。
戦国時代(紀元前403年〜221年)
- 戦国七雄と呼ばれる有力な7つの国(秦・趙・魏・韓・楚・斉・燕)が勢力を争いました。
- 各国は法制度や軍制を整え、強国化を進めていきます。
- 政治、軍事、思想すべてが実力主義に傾いていき、「韓非子」などの法家が影響を強めました。
このように、春秋戦国時代は単なる戦いの歴史ではなく、現代の中国文化や思想の基盤が形成された重要な時代です。
そして『キングダム』は、この中でも最終局面である戦国時代の「末期」に焦点を当てています。
キングダムの時代設定と西暦での位置づけ
キングダムの物語は、紀元前245年頃から始まり、紀元前221年の秦による中華統一までが舞台となっています。
つまり、西暦に直すとおよそ2200年以上も前の古代中国が時代背景です。
この時代設定が重要な理由は、秦という国家が他の国を打ち倒して初めて「統一国家」を築いた歴史的な転換点だからです。
それまでは戦国七雄と呼ばれる国々が競い合っていましたが、物語の中心である嬴政(えいせい)が、やがて中国を一つにまとめていきます。
年表で見るキングダムの時代位置
| 年代(紀元前) | 出来事 |
|---|---|
| 259年 | 嬴政(後の始皇帝)誕生 |
| 247年 | 嬴政が13歳で秦王に即位 |
| 245年頃 | 主人公・信が物語に登場(少年時代) |
| 238年 | 嬴政が成人し、実権を掌握 |
| 230年~221年 | 他国を次々と滅ぼし、秦が統一を果たす |
こうした西暦ベースの視点を持つことで、キングダムが描く歴史の流れがより明確になります。
また同時期の世界では、ヨーロッパではローマが勢力を拡大しつつあり、世界各地で文明が変化し始めたタイミングでした。
歴史のスケールが大きいため、現在と比べると想像しにくいかもしれませんが、現代の価値観にも通じる政治や戦術の駆け引きが多く描かれています。
【個人的メモ】キングダムの時代は三国志より400年前くらい過去の話。今でいうと現代が三国志の時代なら信長とかいた戦国時代くらい昔。司馬尚の子孫は司馬懿、呂不韋の末裔は蜀の呂凱、趙奢・趙括の子孫は馬騰、馬超、馬岱。
— 待宵さんさ (@sansa_hs) February 18, 2025
中国戦国七雄と地図から見る勢力図
キングダムの舞台となる戦国時代には、中国大陸に「戦国七雄」と呼ばれる7つの主要な国が存在していました。
これらの国が互いに勢力争いを繰り広げていたことが、物語の大きな背景になっています。
戦国七雄とは、**秦(しん)、楚(そ)、斉(せい)、燕(えん)、韓(かん)、魏(ぎ)、趙(ちょう)**の7つです。
それぞれの国は地理的に分かれており、地図上で見ると以下のような分布になります。
戦国七雄のざっくりとした位置関係(現代の地理で)
| 国名 | 現在の地名(目安) | 特徴 |
|---|---|---|
| 秦 | 陝西省・甘粛省 | 西方の強国、後に統一を果たす |
| 趙 | 山西省・河北省北部 | 騎馬軍団に強みを持つ |
| 魏 | 河南省北西部 | 中原に位置、戦略的に重要 |
| 韓 | 河南省中部 | 小国ながら外交に長ける |
| 燕 | 北京・遼寧周辺 | 北方で孤立気味 |
| 楚 | 湖北省・湖南省南部 | 広大な領土、文化が豊か |
| 斉 | 山東省 | 経済的に強く、商業国家 |
このように、それぞれの国は地形や位置に応じた戦い方や文化を持っていました。
キングダムでは、こうした地理的要素が戦術や外交にも反映されており、物語に深みを与えています。
例えば、趙との戦いでは「山岳地帯での防御戦」、楚との戦いでは「湿地帯での進軍」などが描かれ、地図と照らし合わせて読むとより理解が深まります。
史実に基づいたキングダムの歴史描写
キングダムの魅力の一つは、物語の多くが実際の歴史に基づいて構成されていることです。
史実とフィクションを組み合わせながら、当時の政治や戦争の動きをリアルに描いています。
なぜこれが重要かというと、ただの空想物語ではなく、実際にあった出来事をベースにしているため、読者は物語を楽しみながら中国の歴史にも自然と触れられるからです。
キングダムが史実に忠実な代表的なポイント
- 嬴政(えいせい)が13歳で秦王に即位したこと
- 呂不韋が一時的に実権を握っていたこと
- 合従軍(がっしょうぐん)との戦いが実際に存在したこと
- 秦が他国を順に滅ぼし、最後に斉を制圧して中華統一を果たした流れ
こうした出来事は、当時の歴史書である『史記』などにも記録されており、登場人物の多くも実在しています。
一方で、完全な史実通りというわけではありません。
例えば主人公・信の行動や感情、個々の戦いの演出には創作が加えられており、フィクションとしての魅力も兼ね備えています。
このため、物語に没入しながらも「これは実際にあったのかも」と思わせるようなバランスが保たれており、歴史に詳しくない読者でも自然に引き込まれる構成になっています。
キングダムがいつの時代かを人物と背景から理解する
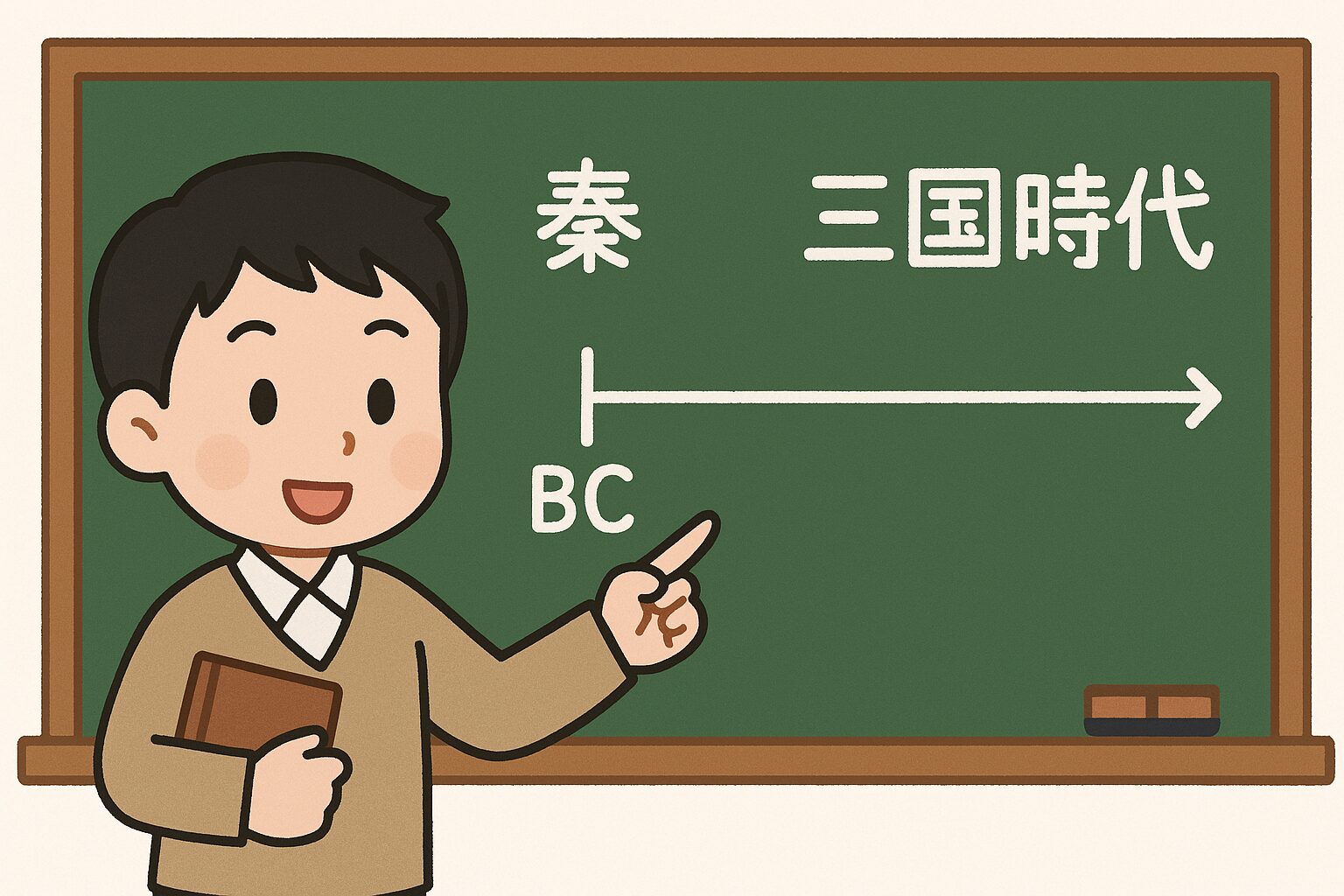
- 信のモデルとなった実在の将軍とは
- キングダムの戦術はどれほどリアルか
- 始皇帝と結末へつながる歴史の流れ
- 三国志とキングダムの時代背景の違い
- ヨーロッパの同時代との比較で見る視野
- 日本でキングダムが時代劇として人気の理由
- 作者・原泰久が描く歴史エンタメの真髄
- キングダムはいつの時代の物語か?まとめ
信のモデルとなった実在の将軍とは
結論から言うと、キングダムの主人公である「信(しん)」のモデルは、実在した将軍「李信(りしん)」とされています。この人物は、紀元前3世紀の秦に仕えた若き将軍で、史実にもその名が記録されています。
信がどのような人物だったのかは詳しい資料が少ないものの、いくつかの記録からその活躍の一端がわかります。
李信将軍の主な史実エピソード
- 秦の将軍として、楚(そ)を攻める遠征軍の総大将を務めた
- 当初、20万の兵を率いて出陣したが、楚軍に敗退
- その後、王翦(おうせん)に交代され、秦は楚を制圧
このように、李信は若くして大軍を任された将軍でありながら、敗戦を経験した人物でもあります。
キングダムでは、彼の成長や失敗を含めた「人間としてのドラマ」が描かれており、それが読者の共感を呼ぶ要素となっています。
前述の通り、史実上の李信に関する情報は限られているため、漫画では大部分が創作で補われています。
しかしその根底には「実在した若き将軍がいた」という事実があり、それが信というキャラクターにリアリティを与えているのです。
キングダムの戦術はどれほどリアルか
キングダムに登場する戦術の多くは、歴史的な軍略や地形、兵種の特徴を元に描かれています。そのため、完全な創作ではなく、現実の戦争で実際に使われた方法を参考にしている場面が多く見られます。
このリアルさが物語に説得力を持たせており、単なるバトル漫画ではなく「戦略ドラマ」としての魅力も際立っています。
漫画に登場する主な戦術・戦い方
- 包囲戦:敵軍を完全に取り囲んで退路を断つ戦法
- 地形利用:山岳や川を活かした防御・待ち伏せ
- 奇襲戦:小部隊による夜襲や裏側からの進軍
- 縦深陣形:後方に控える部隊が前線を補強する構え
例えば、合従軍編では、函谷関という天然の要塞を守るために、大軍同士の駆け引きが繰り広げられます。
このような場面では、部隊の配置や補給路の確保など、戦術のリアルさが強調されています。
ただし、すべてが史実通りというわけではありません。
漫画ならではの演出として、一騎討ちや将軍同士の激しい個人戦が描かれることもあります。これは読者の興味を引くための要素であり、歴史的にはやや誇張された描写といえるでしょう。
このように、キングダムの戦術は現実の軍略をベースにしつつも、物語としての面白さを両立させた構成になっています。
それが多くの読者にとって「学び」と「エンタメ」の両方を感じさせる理由のひとつです。
始皇帝と結末へつながる歴史の流れ
キングダムの物語は、嬴政(えいせい)が中国全土を統一し、「始皇帝」となる歴史的な流れを軸に進んでいます。
そのため、漫画の最終的な結末は、紀元前221年の中華統一という明確なゴールに向かって描かれています。
始皇帝とは、中国で初めて「皇帝」という称号を使った人物です。
それまでは「王」という呼び方が使われていましたが、統一後は他と区別するため、より権威のある名称を自ら名乗りました。
キングダムの結末へつながる流れ(簡易年表)
| 年代(紀元前) | 出来事 |
|---|---|
| 247年 | 嬴政が13歳で秦王に即位 |
| 238年 | 加冠の礼を受け、実権を握る |
| 230~221年 | 韓・趙・魏・楚・燕・斉を順に制圧 |
| 221年 | 中国統一、始皇帝の称号を使い始める |
この流れの中で、キングダムは「戦の勝敗」だけでなく、「政(まつりごと)」や「権力闘争」も丁寧に描いています。
一方で、始皇帝の治世は決して順風満帆ではありません。
統一後は重い税、厳しい法律、民の不満なども生まれ、最終的に秦はわずか15年で滅びることになります。
漫画としてのキングダムはまだ連載中ですが、物語はこの統一の瞬間、つまり始皇帝の誕生を最終章として描かれていくと考えられます。
三国志とキングダムの時代背景の違い
三国志とキングダムは、どちらも古代中国を舞台にしていますが、時代背景は大きく異なります。
結論として、キングダムが描くのは紀元前の「統一前」の時代、三国志は紀元後の「分裂期」です。
時代比較のポイント
| 作品 | 時代区分 | 主な年代 | 状況 |
|---|---|---|---|
| キングダム | 戦国時代(末期) | 紀元前245年〜221年 | 秦が他国を統一へ進む |
| 三国志 | 後漢末期〜三国時代 | 紀元180年〜280年頃 | 漢が崩壊し国が分裂 |
つまり、キングダムは「国家をひとつにまとめる」物語であり、三国志は「ひとつだった国がバラバラになる」物語です。
目的や価値観、人物たちの行動原理も対照的です。
さらに、キングダムは「始皇帝の誕生」が中心ですが、三国志では「曹操・劉備・孫権」の三国が覇権を争います。
また、戦いの規模や武将のスタイルにも違いがあり、三国志はより個人の武勇や戦略家の知略が強調されがちです。
このように、両作品は似ているようでいて、まったく異なる時代背景とテーマを持っています。
だからこそ、それぞれの面白さがあり、読み比べる価値があるのです!
ヨーロッパの同時代との比較で見る視野
キングダムの舞台となる戦国時代の中国は、紀元前3世紀頃です。この時期、世界の他の地域、特にヨーロッパではどのような出来事が起きていたのでしょうか。
実はこの頃、ヨーロッパではローマが勢力を伸ばし始めた時代にあたります。
ローマはまだ帝国ではなく「共和政」と呼ばれる体制で、周辺国と激しく争っていました。
同時代の世界情勢(ざっくり比較)
| 地域 | 状況 |
|---|---|
| 中国(キングダム) | 秦が他の六国を滅ぼし、統一国家を目指す |
| ローマ | ポエニ戦争を経て地中海に勢力を広げる(共和政) |
| ギリシャ | アレクサンドロス大王の死後、分裂と衰退が進行中 |
このように考えると、キングダムの時代は「世界的に大きな動きが起きていた時代」ともいえます。
ただし、当時の中国とヨーロッパは直接的な接触はなく、それぞれが独自に発展していました。
それでも、ローマの拡大やギリシャ文化の広がり、中国の統一などを比べると、
「文明が国家という形を取って拡大していく時代」だったことが見えてきます。
キングダムを読むことで、単に中国の歴史を知るだけでなく、世界全体の動きともつながって考えることができるでしょう。
日本でキングダムが時代劇として人気の理由
キングダムが日本で広く支持されている理由の一つに、「時代劇としての面白さ」があります。
物語の舞台は中国の戦国時代ですが、日本人に馴染みのある「戦」「忠義」「成長」といった要素が強く描かれているため、多くの読者にとって違和感がありません。
このように言うと不思議に思うかもしれませんが、日本の伝統的な時代劇に見られる価値観と、キングダムの描く世界観は重なる部分が多くあります。
キングダムが日本的な「時代劇」と親和性が高い理由
- 忠誠や義を重んじる武将たち:王騎、麃公、蒙武などに見られる精神性は、日本の武士像にも通じます。
- 主人公の成長物語:信が下僕から将軍を目指す流れは、王道のヒーローストーリーとして人気です。
- 戦場の美学と死生観:戦いに散っていく武将の姿は、日本の時代劇にもよく登場します。
- 実写映画・アニメ化による視覚的再現:特に映画では、衣装やセットに「和」を意識した演出も見られます。
このため、舞台は中国でありながら、日本人が持つ「時代劇」への親しみやすさがそのまま当てはまり、ファン層を広げています。
一方で、日本の歴史とは背景が大きく異なるため、馴染みのない人にとっては最初やや複雑に感じる部分もあるかもしれません。
しかし、それを補って余りあるほど、キャラクターや展開の魅力が強く、多くの読者を引き込んでいます。
作者・原泰久が描く歴史エンタメの真髄
キングダムの魅力を語る上で欠かせないのが、作者・原泰久(はらやすひさ)の作家としての手腕です。彼が描く歴史エンタメは、単なる史実の再現ではなく、「人間ドラマ」としての深みを持っています。
結論として、原泰久の作品づくりは、徹底した歴史リサーチと感情に訴える演出のバランスによって成り立っています。
そのため、歴史に詳しくない読者でも楽しめる構成になっているのです。
原泰久の作品スタイルの特徴
- 徹底した資料調査:『史記』などの古典をベースに、人物や時系列を丁寧に再構成
- 現代的な感情表現:キャラクターの葛藤や信念を、読者に共感しやすい形で描写
- テンポの良い展開:歴史の流れに沿いつつ、物語としての緩急がしっかりある
- 映画やアニメへの展開を意識した構成:映像化を前提とした、見せ場のある演出も多数
原泰久はもともとシステムエンジニアから漫画家に転身したという異色の経歴を持っています。
だからこそ、ストーリー構築においても「論理」と「感情」の両方を大切にしながら、エンタメとしての完成度を高めています。
このような作り手のこだわりが、『キングダム』という作品を歴史ファンだけでなく、幅広い層に届く作品へと押し上げているのです。
キングダムはいつの時代の物語か?まとめ
キングダムは、紀元前3世紀の中国・戦国時代末期を舞台にした物語です。
時代としては、秦が他の国々を滅ぼし、中国を統一していく過程を描いています。主人公の信や秦王・嬴政(後の始皇帝)が歴史の中で実在した人物をモデルとしており、物語は史実をベースに展開されています。
この時代は、日本でいえば弥生時代の初期、ヨーロッパではローマが勢力を拡大し始めた頃にあたります。
戦乱の中で仲間とともに成長し、未来を切り開いていく姿が、現代の読者にも強く響く理由のひとつです。
つまり、キングダムは単なる古代中国の物語ではなく、歴史・戦略・人間ドラマが融合した壮大な時代絵巻といえるでしょう!
箇条書きでもまとめました。
- キングダムの舞台は紀元前3世紀の中国・戦国時代末期
- 春秋戦国時代は中国の統一前に続いた長期の戦乱期
- キングダムの時代設定は紀元前245年〜紀元前221年頃
- 戦国七雄(秦・趙・魏・韓・楚・斉・燕)が主要な国家である
- 地理や地形が戦術や国の特徴に大きく影響している
- 嬴政(後の始皇帝)の中華統一が物語の大きな軸になっている
- 主人公・信は実在した将軍「李信」がモデルである
- 戦術描写には史実をベースにしたリアリティがある
- 三国志とは時代背景も物語の方向性も大きく異なる
- 同時代のヨーロッパではローマが拡大期にあたる
- キングダムは日本で時代劇としても親しまれている
- 作者・原泰久の構成力と歴史考証が作品の魅力を支えている


