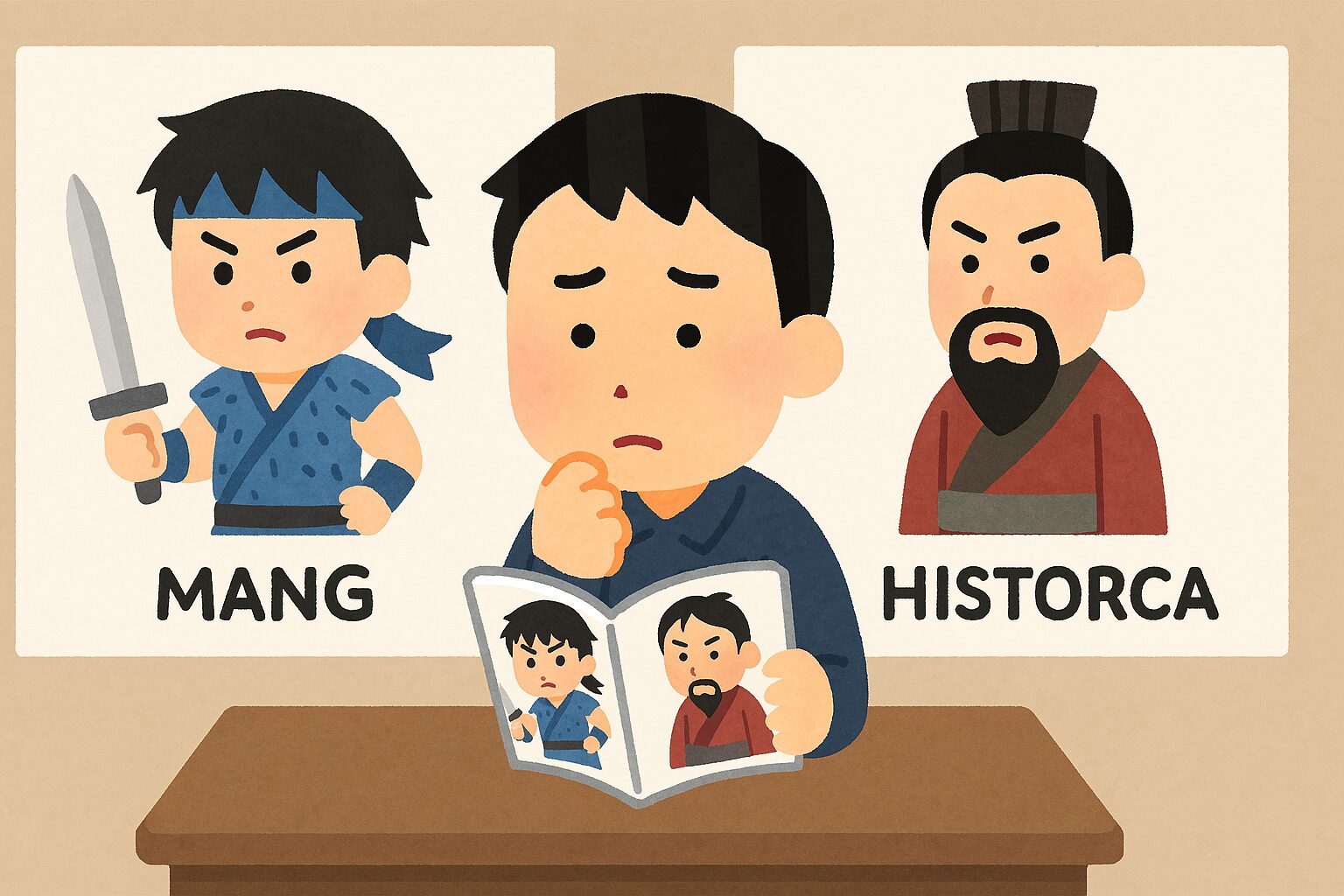
『キングダム』は、壮大なスケールで戦国時代の物語を描く人気作品ですが、その魅力のひとつが「史実との違い」を楽しめる点にあります。
作中で描かれる信(李信)や嬴政(えいせい)、呂不韋(りょふい)、李朴などの人物たちは実在した歴史上の人物ですが、そのキャラの性格や関係性には大きな脚色が加えられています。また、羌瘣(きょうかい)や一部の実在しないキャラも物語を盛り上げる要素として重要な役割を果たしています。
この記事では、キングダムと史実の違いを丁寧に解説しながら、実際の年表や歴史の流れをもとに、李信は六大将軍だったという史実はあるのか、李信の嫁についての情報、さらには龐煖(ほうけん)の正体や滅びる順番の背景まで、幅広く紹介していきます。
ネタバレ要素を含みますのでご注意のうえ、作者が描いた創作の魅力と、史実との違いを一緒に楽しんでいきましょう!
結論!史実との主な違い
| 項目 | キングダム(フィクション) | 史実(事実) |
|---|---|---|
| 信(李信) | 下僕出身の熱血主人公。天下の大将軍を目指す青年。 | 名門出身の秦の将軍。楚戦で敗北し、後に燕・斉攻めに従軍。 |
| 羌瘣(きょうかい) | 女剣士。飛信隊副長で信の相棒的存在。 | 将軍として記録があるが、性別・経歴不詳。作中の設定は創作。 |
| 嬴政(始皇帝) | 理想高き若き王。人の本質を信じる人格者。 | 冷酷な独裁者。粛清や重税、万里の長城建設など圧政で知られる。 |
| 王翦 | 謎多き策士型の老将軍。信との対比存在。 | 慎重な戦略家で楚滅亡の功労者。猜疑を避けつつ忠義を尽くす。 |
| 李牧(りぼく) | 寡黙な天才軍師。信の宿敵として描写。 | 趙の名将。匈奴・秦を撃退し、王の讒言で処刑される。 |
| 楊端和 | 女性の山の王。飛信隊の盟友的存在。 | 実際は性別不明。秦に仕えた男性将軍とされる。 |
| 合従軍との戦い | 王騎・信・政の活躍が描かれ、咸陽防衛の死闘。 | 実際にあったが、嬴政の出陣などは完全な創作。 |
| 六大将軍制度 | 信・王賁・蒙恬らの「新六大将軍」が任命される。 | 史実にそのような制度や李信が選ばれた記録はない。 |
| 恋愛・人間関係描写 | 信と羌瘣の関係、羌瘣の過去、飛信隊の絆などが中心。 | 史書に記録なし。キャラの人間関係は大半が創作。 |
| 登場人物の死 | 王騎・麃公・成蟜など感動的に描写される。 | 史実では戦死・粛清の記録はあるが、詳細や感情描写はない。 |
| 作中時代の流れ | 紀元前245年ごろから順に国を滅ぼしていく。 | 滅亡の順番:韓→趙→燕→魏→楚→斉(前230〜221年) |
| 飛信隊メンバーの多く | 魅力的な創作キャラクター(河了貂・渕・シュンメンなど) | 史実に存在しないフィクション。 |
| 李信の妻・恋愛描写 | 羌瘣との関係が進行中。 | 李信の妻については記録がないが、名家の女性と推測される。 |
キングダムと史実の違いを総解説
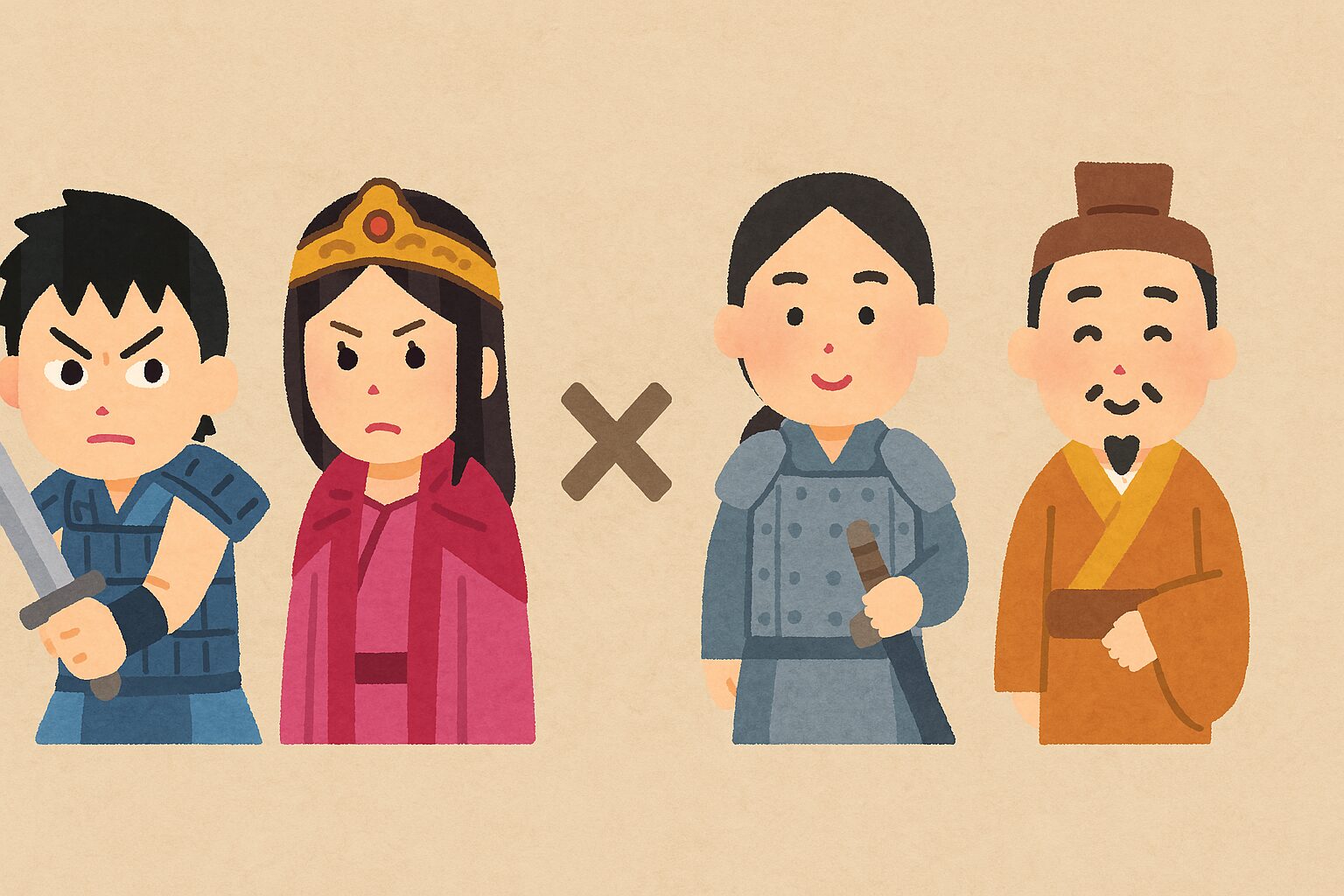
- 史実とフィクションの比較ポイント
- キングダムの年表で見る歴史の流れ
- 信は実在した?人物像と史実の違い
- 李信は六大将軍だったという史実はある?
史実とフィクションの比較ポイント
結論から言えば、『キングダム』は中国戦国時代の史実をベースにしながらも、多くの場面でフィクションが加えられた作品です。
そのため、物語としての面白さはありますが、すべてが歴史の通りというわけではありません。
まず理由として挙げられるのは、史実の資料が限られていることです。特に戦国末期の出来事は『史記』などの記録に簡潔にしか書かれておらず、登場人物の性格や会話、戦いの詳細な様子までは残されていません。この隙間を埋める形で、創作が加えられているのです。
具体的な例として、主人公の信(李信)は実在した武将ですが、下僕出身という設定はフィクションです。実際の李信は秦の将軍として複数の戦いに参加し、始皇帝にも信頼されていた人物とされています。ただし、その人物像や活躍の詳細は記録に乏しく、作中のような英雄譚になっているかは定かではありません。
また、戦の描写にも違いがあります。例えば合従軍との戦いでは、作中では壮大な戦略や一騎打ちが展開されますが、実際には大将同士が戦場で直接戦うことは少なく、部隊の総合力や外交が勝敗を分けていました。
史実とフィクションの違いを整理
| 要素 | キングダム | 史実 |
|---|---|---|
| 信の出自 | 下僕から成り上がった少年 | 出自は不明だが、名門の可能性が高い |
| 合従軍との戦い | 政や信が前線に出て戦う描写が中心 | 実際には政は戦場に出ていない |
| キャラクターの性格 | 読者に感情移入しやすいよう脚色されている | 多くは性格の記録がなく、創作されている |
| 一騎打ちの場面 | 多数登場し、戦のクライマックスとして描かれる | 現実の戦争では大将同士の一騎打ちは稀 |
このように、歴史的な大枠を踏まえながらも、読者が物語に没入できるよう数多くのフィクションが織り交ぜられています。
歴史を知る入り口として『キングダム』を楽しむことは有意義ですが、事実とは異なる部分も多いため、正確な歴史を学びたい場合は別途史書を参考にする必要があります。
キングダムの年表で見る歴史の流れ
キングダムの物語は、紀元前245年ごろから始まり、最終的には秦が中国を統一する紀元前221年までを描いています。これは実際の戦国時代後期に当たる期間であり、史実の流れと大きく一致しています。
まず結論として、この年表の流れを把握することで、『キングダム』がどこまで史実に基づいているかを確認しやすくなります。さらに、今後の展開を予測する材料にもなります。
理由として、この時代は「戦国七雄」と呼ばれる秦・楚・斉・燕・趙・魏・韓の七か国が覇権を争っており、秦が順に他国を滅ぼしていく過程が物語の主軸になっているためです。
キングダムと史実の流れを比較した年表
| 年代(紀元前) | 史実の出来事 | キングダムでの描写 |
|---|---|---|
| 約245年 | 信と漂の下僕時代(創作) | 漫画第1巻〜:王都奪還編スタート |
| 241年 | 合従軍の侵攻と函谷関の戦い | 合従軍編として詳細に描写 |
| 230年 | 韓が秦により滅亡 | 作中でも戦略的な滅亡過程が描かれる |
| 228年 | 趙が滅亡(李牧の処刑が前提) | 李牧との戦いが継続、改変の可能性あり |
| 226年 | 燕が滅亡 | 信が丹を討つ描写が予想される |
| 225年 | 魏が滅亡 | 漫画では未描写、今後の展開候補 |
| 223年 | 楚を王翦が滅ぼす | 信の敗戦と王翦の活躍が描かれる可能性 |
| 221年 | 斉を滅ぼし、秦が中華統一を達成 | 最終章として描かれる見込み |
このように、物語は史実とほぼ同じ順番で国が滅びていく流れになっています。ただし、各戦いの描写や人物の関与は創作も多く含まれているため、歴史の流れをなぞりながらも『キングダム』独自の解釈がある点には注意が必要です。
また、年表をもとに物語を追うことで、今後登場するであろう重要人物や戦の予習にもなります。歴史ファンにとっては、どこが事実でどこが創作なのかを照らし合わせる楽しさもあるでしょう。
信は実在した?人物像と史実の違い
結論として、キングダムの主人公・信のモデルとなった「李信(りしん)」は、実在した歴史上の人物です。ただし、漫画で描かれているような下僕出身の少年という設定や、数々の英雄的な活躍の多くは創作です。
その理由は、史実における李信に関する記録が非常に限られており、生い立ちや人柄などが詳しく伝えられていないからです。『史記』などでは、彼は秦の将軍として登場し、特に中華統一戦争に関わった将軍の一人として名前が挙げられています。
具体的な史実に基づく李信の実績
- 始皇帝の時代、燕や斉を攻略する軍に参加
- 楊端和や羌瘣と共に趙の邯鄲を攻める際、北部で別働隊を指揮
- 蒙恬と共に20万の兵を率いて楚を攻撃するが大敗
- 最終的に王翦・王賁と共に統一戦争を締めくくる役割を果たす
一方で、漫画では「信」は下僕から将軍へと成り上がるサクセスストーリーが描かれています。この点については記録がなく、実際の李信がどのような身分出身であったかは不明です。ただし、秦の将軍にまで昇進していることから、少なくともある程度の家柄だった可能性が高いと考えられています。
このように考えると、「信」というキャラクターは史実をベースにしつつも、読者が共感しやすいように大きくアレンジされた存在だと言えるでしょう。物語をドラマチックにするための工夫と理解して読むことで、より楽しめます。
李信は六大将軍だったという史実はある?
結論から述べると、「李信は六大将軍の一人であった」という史実は存在しません。この設定は漫画『キングダム』オリジナルの創作です。
理由として、史実には「六大将軍制度」そのものの明確な記述がないためです。かつての白起や王翦のような名将たちを「六大将軍」と呼ぶ表現はファンの間や創作作品で使われることがありますが、当時の制度として確立されていた証拠は見つかっていません。
漫画では、信(李信)・蒙恬・王賁など若手の有望株が「新・六大将軍」として任命される展開があります。しかし、これは史実では確認されておらず、作品の演出として登場人物の成長を描くために設定された役割です。
史実上の李信の立ち位置
- 名将・王翦の下で作戦に参加することが多かった
- 蒙恬と共に重要な作戦を任されるなど信頼は厚かった
- 統一戦争後も一定の功績を残しているが、大将軍として記録されてはいない
つまり、実際の李信は確かに有能な将軍ではありましたが、「六大将軍」といった特別な称号が与えられたわけではありません。したがって、漫画での設定は、彼の歴史的ポジションを強調するための物語上のアレンジです。
このように、作品の演出としての「六大将軍」はドラマ性を高める要素であり、史実と混同しないよう注意することが大切です。
キングダムと史実の違いが見えるキャラと物語展開
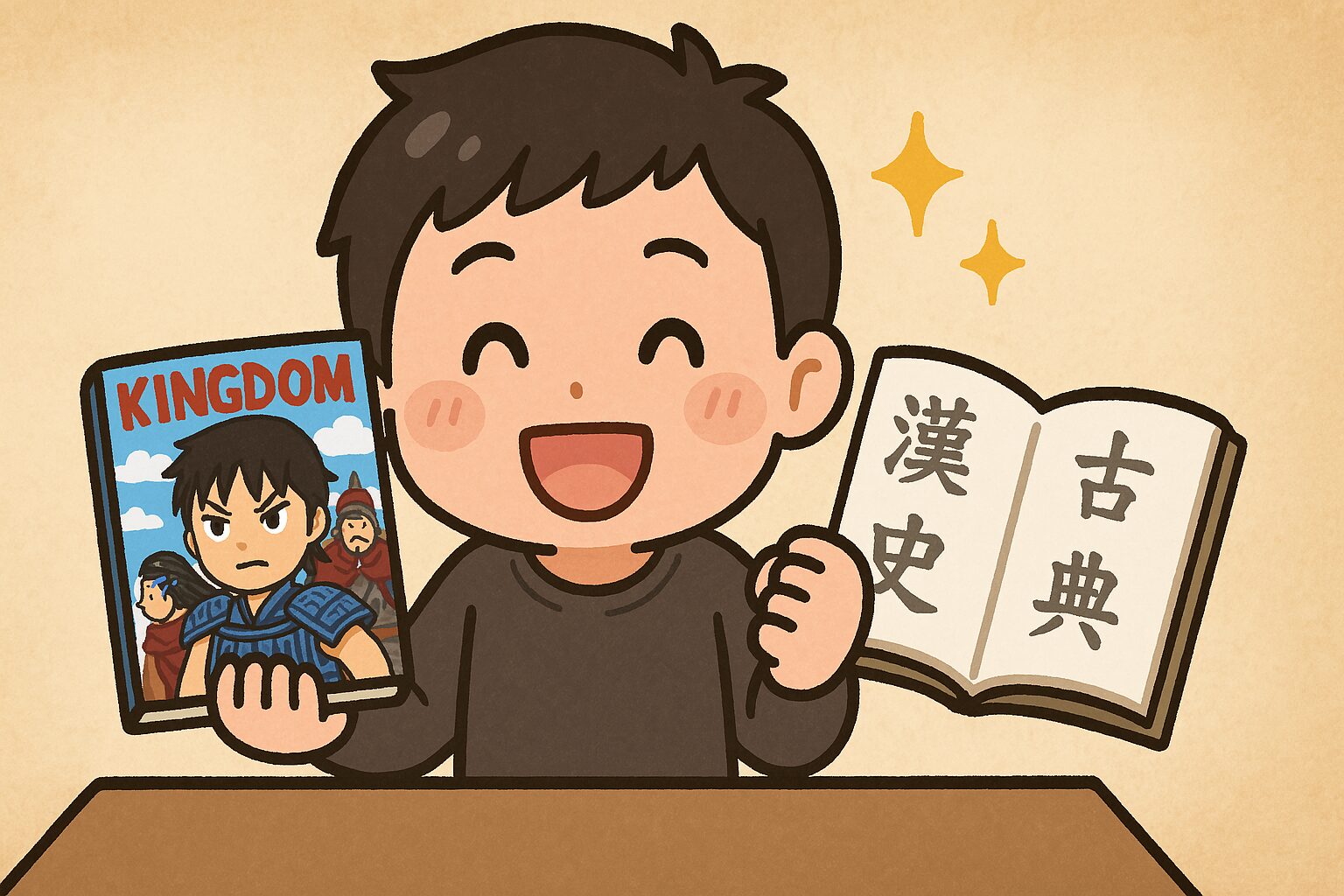
- 実在しないキャラの特徴と役割
- 羌瘣(きょうかい)は実在した将軍か?
- 嬴政(えいせい)は本当に理想の王?
- 呂不韋(りょふい)の人物像と史実比較
- 龐煖(ほうけん)の正体と戦国での役割
- キャラの性格は史実とどれほど違う?
- 李朴(李牧)は本当に名将だったのか?
- 李信の嫁は史実ではどう記されている?
- キングダムのネタバレ:史実とのリンク
- 戦国七雄が滅びる順番と史実の根拠
- キングダムの作者が語る史実との向き合い方
- キングダムと史実との違いまとめ
実在しないキャラの特徴と役割
『キングダム』には多くの魅力的なキャラクターが登場しますが、その中には史実に存在しないキャラも少なくありません。結論として、これらのキャラクターは主に物語を盛り上げたり、読者の感情移入を促すために登場しています。
その理由は、実際の歴史書には人物の詳細な性格や人間関係、心の動きなどがほとんど記録されていないためです。物語に深みや人間味を持たせるには、創作されたキャラクターの存在が不可欠なのです。
主な実在しないキャラの例と役割
| キャラ名 | 主な役割と特徴 |
|---|---|
| 河了貂(かりょうてん) | 飛信隊の軍師として信を支える。コミカルで親しみやすい存在。 |
| バジオウ | 山民族の戦士。楊端和を支える忠義の猛将として活躍。 |
| 輪虎(りんこ) | 趙の将軍。信や王騎と対峙する強敵として登場。 |
| シュンメン | 政の護衛。無口ながら信頼の厚い存在。 |
| 黒桜(こくおう) | 桓騎軍の幹部で冷酷な女戦士。狂気じみた戦闘スタイルでインパクトを与える。 |
| 麻鉱(まこう) | 秦の将軍。物語の展開上、戦死することで政権の緊張感を高める役割を担う。 |
これらのキャラクターは、物語上の「オリジナル要素」として非常に重要です。特に信の仲間である飛信隊のメンバーはほとんどが創作で、チームとしての結束や感情的な盛り上がりを支える存在となっています。
一方で、実在しないキャラが多すぎると、史実との混同を招く恐れもあります。そのため、『キングダム』を読む際には「誰が実在し、誰が創作なのか」を意識しながら楽しむことが大切です。
羌瘣(きょうかい)は実在した将軍か?
結論として、羌瘣(きょうかい)が実在したかどうかははっきりしていません。彼女に関する明確な記録はなく、史実上の存在かどうかは不明です。
その理由として、羌瘣という名前は一部の資料で「秦の時代に将軍として活躍した羌族の人物」に由来するとも言われていますが、その詳細は残っていません。性別についての記述もなく、作中で描かれている「女性剣士」「巫舞を使う暗殺一族の出身」という設定は創作と考えられます。
作中の羌瘣の特徴と役割
- 元・幽連一族の暗殺者でありながら、信の仲間として飛信隊に加わる
- 飛信隊の副長として戦場で活躍し、信と深い絆を築く
- 巫舞によって身体能力を限界まで高め、一騎打ちで数々の武将を打ち破る
- 過去に姉を亡くした悲しい背景を持ち、復讐から仲間との未来へと心境が変化していく
このように、羌瘣は「強くて美しい女性キャラ」として、物語に緊張感とドラマ性をもたらしています。彼女の存在はフィクション色が強いですが、それによって飛信隊のストーリーに深みが生まれ、読者に強い印象を残しています。
一方で、史実では女性が戦場で将軍として活躍する記録は非常に少なく、秦の時代にはほとんど例がありません。そのため、羌瘣のキャラクターは完全に史実に基づいているわけではなく、物語上の創作である可能性が極めて高いと考えられます。
嬴政(えいせい)は本当に理想の王?
結論から言えば、嬴政(後の始皇帝)は史実においても非常に優れた統治者でしたが、必ずしも「理想の王」とは言えない側面もあります。『キングダム』では、民を想い改革を進める若き名君として描かれていますが、史実では苛烈な手法を用いた支配者でもありました。
その理由として、嬴政は中華統一という大業を成し遂げるために、徹底的な中央集権体制を構築し、反乱の芽を摘むための過酷な制度を導入したからです。これは大きな成果である一方、自由の制限や重税、労役の強制をもたらしたことも事実です。
嬴政の主な業績と現実的な評価
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 中華統一 | 紀元前221年、戦国七雄をすべて滅ぼし、史上初の統一国家「秦」を樹立 |
| 中央集権体制 | 郡県制の導入で地方を王が直接支配できる体制を整備 |
| 文化・制度統一 | 度量衡、文字、通貨、車幅などを統一し、経済と行政の基盤を築いた |
| 法による統治 | 法家思想を採用し、法による厳格な統治を実施(反面、弾圧も強化) |
| 万里の長城の建設 | 匈奴の侵攻を防ぐために建設を推進。ただし過酷な労働が民に重くのしかかった |
『キングダム』では、嬴政の人間的な魅力や理想に燃える姿が強調されていますが、史実では「恐怖と法」で支配した側面もありました。つまり、理想の王というよりは「成果を重視する実務的な支配者」として見るのが適切でしょう。
呂不韋(りょふい)の人物像と史実比較
呂不韋は、物語の序盤から登場する重要人物です。結論として、漫画でも史実でも非常に影響力のある政治家でしたが、評価は大きく分かれています。
その理由は、彼の行動が「秦の発展に貢献した」とも「私利私欲のためだった」とも取れるからです。『キングダム』では知略に富みつつも野心を隠さない政治家として描かれますが、史実でも同様に、嬴政の父・子楚を擁立し、その後の権力を握った人物とされています。
呂不韋の主な実績と特徴
- 商人出身で、子楚(嬴政の父)を政治的に支援し太子にする
- 嬴政即位後は実質的な宰相として秦を動かす
- 『呂氏春秋』という思想書を編纂し、思想界にも影響を与える
- 嫪毐事件によって政との関係が悪化し、最終的に失脚・自害
呂不韋の評価は「優れた改革者」とも「策謀家」とも言われます。キングダムでは、政との対立が物語を大きく動かす要因の一つとなっていますが、史実でもその影響力の大きさは疑いようがありません。
ただし、政が自立するにつれて呂不韋の影響力は減り、最終的には政権から退かされました。この点でも、野心を持つ者の限界と権力の移り変わりを象徴する存在ともいえるでしょう。
龐煖(ほうけん)の正体と戦国での役割
龐煖(ほうけん)は、漫画では「武神」と呼ばれ、圧倒的な戦闘力を持つ求道者として描かれています。しかし、結論から言うと、史実では現在のような戦闘狂のキャラクターではなく、政治家・外交官としての顔が主でした。
理由は、『戦国策』や『史記』の記述において、龐煖は合従軍の編成を行うなど、戦略面で活躍した記録が中心であるためです。一騎打ちを好む孤高の戦士という描写は、創作の要素が強いと考えられます。
史実における龐煖の役割
- 合従軍の中核を担い、秦に対抗するため複数国をまとめ上げた
- 合従軍の作戦指導に携わり、外交的手腕があったとされる
- 合従軍敗北後は表舞台から消えるが、秦にとって大きな脅威であった
一方で、『キングダム』における龐煖は、王騎や信、李牧などとの一騎打ちを通して「人の本質とは何か」を問い続ける哲学的な存在になっています。このようなキャラクター造形は、物語に深みを与える創作であり、実在の龐煖とは大きく異なるものです。
まとめると、史実の龐煖は知略に優れた外交官であり、漫画のような超人的な武人ではなかったという点が大きな違いです。作品内での存在感は圧倒的ですが、実際には言葉で国を動かす人物だったと見るのが自然です。
キャラの性格は史実とどれほど違う?
『キングダム』に登場するキャラクターたちは、史実をベースにしているものの、その性格や行動には大きな脚色が加えられています。結論から言うと、史実でわかっているのは彼らの功績や地位などの断片的な情報であり、性格は作者による創作が多くを占めています。
これは物語としての魅力を高めるための手法です。読者が共感しやすいように、あるキャラは情熱的に、またあるキャラは冷静沈着に描かれていますが、実際にそうだった証拠はほとんどありません。
主なキャラの性格の違い例
| キャラクター | 漫画での性格 | 史実の記録との違い |
|---|---|---|
| 王翦(おうせん) | 冷徹で無口な戦略家 | 実際には忠誠心の厚い慎重な名将とされる |
| 李信(りしん) | 熱血で直情的な若者 | 史実では名門出身で実務に長けた将軍 |
| 嬴政(えいせい) | 理想に燃える若き王 | 統一後は厳格で恐怖政治的な一面も強かった |
| 龐煖(ほうけん) | 武を極める孤高の求道者 | 実際は合従軍の編成に関与した外交官的な人物 |
| 呂不韋(りょふい) | 策略家で権力志向の政治家 | 実際にも野心的で、宦官事件など権力争いに関与 |
このように、キャラの性格はあくまで物語をドラマチックにするための設定です。史実とは異なる面があることを理解して読むことで、より冷静に物語を楽しむことができます。
李朴(李牧)は本当に名将だったのか?
李牧(りぼく)は、『キングダム』でも屈指の強敵として描かれますが、史実でも実力派の名将だったことは間違いありません。結論として、彼は趙国を最後まで支えた将軍であり、その戦術と防衛能力は高く評価されています。
その理由は、匈奴や秦といった強敵に対して複数回勝利し、戦局を有利に進めた記録が残っているためです。特に、秦の大将・桓騎を破った戦いは有名で、趙にとって重要な防衛線を守り抜いた功績があります。
李牧の史実における実績
- 匈奴を撃退し、趙の北辺を安定させた
- 桓騎軍を撃退し、秦に大損害を与えた
- 番吾の戦いで秦軍を再び破るなど、対秦戦で複数の勝利を記録
- 秦の王翦による総攻撃に対し善戦するも、最終的には国内の陰謀により処刑
つまり、戦場での功績だけでなく、内政においても有能な将だったと考えられます。ただし最終的には、王命を拒否して処罰されたと伝えられ、その死は秦による反間策(スパイの策略)によるものとされています。
これらの背景から、李牧はただの軍人ではなく、国家戦略の中核を担う存在であり、その力量は「名将」と呼ぶにふさわしいものだったといえるでしょう。
李信の嫁は史実ではどう記されている?
李信の妻については、史実に具体的な記録はほとんど残っていません。結論として、彼の家族構成や結婚に関する詳細な情報は不明であり、『キングダム』で描かれるような人物像は創作である可能性が高いです。
その理由は、史書『史記』や『戦国策』などの主要な歴史資料において、李信自身の軍事行動については記載があっても、私生活についてはほぼ記述がないからです。
漫画での描写との違い
- 『キングダム』では、羌瘣(きょうかい)との関係がロマンスとして描かれる兆しがある
- 現時点では結婚には至っていないが、将来的な描写の可能性がある
- 飛信隊の仲間との絆を強調する中で、嫁に該当する女性キャラが感情面の支えとして描かれている
一方で、史実では李信の子孫が前漢の名将・李広であるという説があり、一族は代々将軍職を務めていたとされています。ただし、その間にどのような家族がいたのかは不明で、史実として「誰と結婚したか」「どんな妻だったか」は確認されていません。
このように、李信の嫁に関する情報はフィクションで補完されている部分が多く、漫画では読者が感情移入しやすいように描かれていると理解するのがよいでしょう。
キングダムのネタバレ:史実とのリンク
『キングダム』は史実をベースにしているため、大まかな歴史の流れや主要人物の運命については、ある程度先の展開が予測できます。つまり、史実を知っていれば、物語の「ネタバレ」になってしまう可能性があるのです。
その理由は、作品が中国戦国時代末期の「秦の中華統一」を描いているため、実際に何が起こったのかが史書で確認できるからです。例えば、李信が楚に敗れることや、王翦が最終的に中華統一に貢献することなどは、史実通りに描かれる可能性が高いエピソードです。
史実とリンクする主な展開
- 李信の敗北と王翦の登板:楚攻めで李信が失敗し、王翦が後任として成功する流れ。
- 王騎や麃公の戦死:史実には明確な記録はありませんが、物語上は史実と整合性を保つ形で退場。
- 六国滅亡の順序とその手法:実際の戦略や政治工作をベースに展開されている。
- 嬴政の中華統一と始皇帝即位:物語の最終目標として据えられている。
このように、歴史に忠実な展開がある一方で、キャラの個性や戦術描写などは創作であるため、史実を知っていても物語を楽しむ余地は十分にあります。
戦国七雄が滅びる順番と史実の根拠
戦国七雄とは、秦・楚・斉・燕・趙・魏・韓の七つの国を指します。『キングダム』でもこの七雄が主な舞台ですが、史実では滅亡した順番がはっきりと記録されています。
結論から言うと、以下の順で秦によって滅ぼされました。
戦国七雄の滅亡順と年表
| 順番 | 国名 | 滅亡年(紀元前) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韓 | 前230年 | 最初に滅ぼされた弱小国 |
| 2 | 趙 | 前228年 | 李牧の死後、王翦らによって攻略 |
| 3 | 燕 | 前226年 | 薊(けい)陥落で実質崩壊 |
| 4 | 楚 | 前223年 | 王翦と蒙武が大軍を投入して滅ぼす |
| 5 | 斉 | 前221年 | 抵抗せず降伏、中華統一が完了 |
| 6 | 魏 | 前225年 | 蒙驁が黄河を使った戦術で水攻め |
この滅亡の順番は、『キングダム』の今後の展開にも大きく関わってきます。そのため、史実を知っておくことで、次にどの国が舞台になるのか、どのキャラが活躍するのかを予想するヒントになります。
一方で、物語では戦略や人間ドラマが加えられているため、史実通りの流れでも新鮮な驚きが生まれるように描かれています。
キングダムの作者が語る史実との向き合い方
『キングダム』の作者・原泰久氏は、作品の執筆において「史実バリアー」という独自のスタンスを取っています。これは、史実として確定している事実(例えば戦の勝敗や登場人物の生死など)を変更せずに、そこに至る過程を自由に創作するという考え方です。
このような方針を取っている理由は、歴史の面白さとエンターテインメント性を両立させるためです。史実の流れに忠実であることで、読者に信頼感を与えつつ、創作部分でドラマ性や感情の深さを描くことができるのです。
作者が意識しているポイント
- 結果は変えない:勝敗や滅亡は史実通り
- 過程を魅せる:キャラの想いや葛藤に重点
- 読者の感情を動かす:友情、成長、別れなどの演出
例えば、蕞(さい)での嬴政の演説や、王騎の死の描写は完全にフィクションでありながら、史実の背景をふまえて読者の心を動かす名シーンとなっています。
このように、原氏は史実と創作のバランスを綿密に取りながら、読者が「歴史を知る喜び」と「物語に泣ける感動」の両方を得られる作品作りを目指しているといえます。
キングダム、壁が誤訳と判明して途中から架空のキャラになったのウケてしまった
— 0371 (@_cab8d9) February 20, 2020
史実通りに進めなきゃいけないのを作者が「史実バリアー」って言ってんのもウケてしまった
キングダムと史実との違いまとめ
『キングダム』は中国戦国時代の実在する出来事をもとに描かれた作品ですが、物語の面白さを引き出すために多くの創作が加えられています。
大きな歴史の流れや人物の功績は史実に準じている一方で、登場人物の性格や細かなエピソード、戦術の演出などにはフィクションが多く含まれています。
違いの要点まとめ
- 人物設定:性格や出自、関係性などに脚色が加えられている
- 戦いの描写:戦術や戦場の演出は創作要素が強い
- 史実との一致点:戦国七雄の滅亡順や主要な戦の結果は基本的に史実通り
- 実在しないキャラ:物語を盛り上げるためのオリジナルキャラも多数登場
- 作者の方針:史実の“結果”は守りつつ、そこまでの“過程”を自由に創作
このように、『キングダム』は史実とフィクションのバランスをとりながら構成された作品です。
史実との違いを理解することで、より深く物語を楽しめるようになるでしょう!
箇条書きでもまとめました。
- 『キングダム』は史実をベースにしつつ多くのフィクションが加えられている
- 李信は実在の武将だが、下僕出身などの設定は創作
- 合従軍との戦いや一騎打ちの描写はドラマ的な演出が強い
- キャラの性格や人間関係は史実に基づかず脚色されている
- 羌瘣など実在しないキャラが物語に深みを与えている
- 史実上の「六大将軍制度」は存在せず、完全なフィクション
- 嬴政や呂不韋の人物像も史実と描写に大きな違いがある
- 年表の流れは史実と概ね一致しており、滅亡順も同様
- 作者は「史実の結果は守り、過程を創作する」スタイル
- 『キングダム』は歴史の入口としては有効だが正確な学習には不向き






